INTERVIEW 009
GRADUATE
菅野創
メディアアーティスト
AI/IoT時代に、人と機械の関係性を問う
今年3月、第21回文化庁メディア芸術祭で、『アバターズ』(やんツーとの共同制作)がアート部門優秀賞を受賞した菅野創さん。車や電話など日常にあるモノの「環世界」を体感できる実験的な今作をはじめ、IoT時代における人と機械のありようを問う作品を多く制作してきた。
第15回文化庁メディア芸術祭で『SENSELESS DRAWING BOT』(やんツーとの共同制作)が新人賞を受賞後、2013年に海を渡り、現在もベルリンを拠点に作品制作を続けるメディアアーティストの本音に赤羽亨准教授が迫った。
モノに“憑依”し、新たな知覚を体感する
赤羽:文化庁メディア芸術祭の受賞おめでとうございます。
菅野:ありがとうございます。
赤羽:今回受賞した『アバダーズ』はどのような作品ですか。
菅野: IoT化が進み、あらゆるものにコンピュータが入ってくると、サーバに繋がるコミュニケーション能力や伝達能力、環境を知覚する知能やそれを処理する知覚など、モノが“知覚”を持つようになります。すると人間は本能的にモノにパーソナリティがあるように錯覚してしまうんですよね。モノがインテリジェンスを持って動き始めたり、モノが人間を見るという状況が生まれるということを、単にクリティカルに、ではなく?、少しコミカルに表現した作品です。
会場には、インターネットと接続した、車や観葉植物、カラーコーン、石膏像など、大きさや視点の高さの違う、様々な自然物、人工物が配置されていて、鑑賞者はWEBサイトからログインして、僕らはそれを“憑依”と呼んでいるのですが、各オブジェクトを操作したり、モノについているカメラやマイクでモノの近く世界を体感することができます。

『アバターズ』菅野創+やんツー 撮影:古屋和臣 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]
赤羽:この作品は会場に来る人とWEBサイトから接続した人の両方を鑑賞者と呼んでいるのですか?
菅野:そうですね。両方を体験して初めて理解できる作品になっています。
赤羽:実際には、鑑賞者は両方を体験しているのですか。
菅野:山口情報芸術センター[YCAM]で展示した時は、来館者が約1万5千人くらいで、WEBに来たのは約7千人でしたね。
赤羽:え!?来館者の方が多いんですね。
菅野:そうです、来館者の方が多いです。YCAMではホワイエというコミュニケーション空間で展示したことも影響したかもしれません。ホワイエは普段は高校生などが勉強しにくるようなオープンな場所なので、最後の方は展示中にもかかわらず、そこでご飯を食べてるみたいなこともありました。今回のメディア芸術祭は美術館なので展覧会風のコードにしていますが、完全にパブリックに公園で展示するのもおもしろいかなと思っています。

『アバターズ』菅野創+やんツー 撮影:古屋和臣 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]
赤羽:そちらの方がいいと思います。YCAMに来ている高校生とかが、初めて見た時から、そこにあることがだんだん普通になっていくのはおもしろいですね。関わり方が変わってくるということが、この作品に関しては肝のような気がします。
あとは、鑑賞者に前提となる知識がないと関係性が理解できない場合があるんじゃないかなと思います。向こう側に明らかに憑依しているユーザーがいて、それが動いていると認識しながら見るのと、そうは言われているんだけど、実際はランダムに動いてた場合、受ける印象が実際はあまり変わらないかもしれないというのはありますよね。
菅野:それは僕も興味があるところで、ゴーストモードという過去に入れられたコマンドを勝手に再生して動いている時もあります。その違いは見ている方には分からない。
赤羽:それがいいね。つまりタイムマシーンみたいなものですよね。時間も空間も共有していない人のふるまいがここにあるという。
菅野:そうそう。そういう気配があるんですと伝えると、人間ってそれを知覚するんですよね。そこはおもしろいなって思います。
赤羽:そこは僕もおもしろいと思う。
菅野:それはこの作品の一部というか、作品の大事なところです。

赤羽:この作品はやんツーさんとの共作ですよね。どういう役割分担で作品を作っているのですか。
菅野:僕らは、それぞれのアイデアを雑に繋げたらおもしろい作品になったということが結構あります。今回は、やんツーは2Dでドローイングをずっとやっていたので、3次元で何かものを動かすことがやりたいと言っていて、僕はロボットをたくさん使うことに興味を持っていた時期だったので、2人のやりたいことを合わせて「モノをロボットにしよう」ということになりました。
そうしたら、ヤーコプ?フォン?ユクスキュルの『環世界』とか、カフカの『変身』とか、トマス?ネーゲルの『コウモリであるとはどのようなことか』とか。つまり、自分の見た目が変化することにより世界の知覚の仕方が変化するというような、色々な可能性が見つかって、これはおもしろそうだと大枠のアイデアが定まっていきました。
赤羽:なるほど。
菅野:作業的な担当については、基本的にハードとソフトで分けています。今回はハードソフトもコアな部分はYCAMインターラボに手伝っていただいています。
赤羽:いろいろな人が関わっているプロジェクトなんですね。これまでの作品も、ひとりで作った作品はほとんどないですよね。
菅野:ないですね。今回は特にかなりたくさんの人と作ったプロジェクトです。関わる人数が多いとできることも多くなるので、そういうプロジェクトはこれからもやっていきたいなと興味が出てきました。
分水嶺に立つ34歳
アーティストを続けていく難しさ
赤羽:現在の拠点はドイツのベルリンだそうですが、IAMASを卒業してから、ベルリンに至るまでの経緯を聞かせてください。
菅野:卒業後は、1年間研究生をしていました。その時に、多摩美術大学の助手の募集があり、レーザーカッターや3Dプリンタなどの機材担当として2年間勤務しました。
2年目の時に、やんツーと協同制作した『SENSELESS DRAWING BOT』が文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞して、このタイミングで任期を更新せず、フリーランスでやってみようと、退職しました。

『SENSELESS DRAWING BOT』菅野創+やんツー
赤羽:菅野は、IAMASに入った当初は、おそらくメカニカルなことを知っている訳でもなく、技術もほとんど持っていなかったと思うんだよね。「ガングプロジェクト」で『Jamming Gear』を作った時に、3Dプリンタやレーザーカッターを使い倒して、その時の技術が今にまで繋がってるんじゃないかなと感じています。
菅野:確かに。本当にありがたかったです。プリンタやレーザーカッター、ミリングマシンを、あの当時は「自分が一番使えている」という自負がありました。最初はプログラムも(小林)茂さんに書いてもらっていたんですけど、ある時に一念発起して書き始めたら、「茂さん、書けるようになりました!」って感じでしたね。
赤羽:多摩美の助手を辞めてからは何をしていたのですか。
菅野:1年間フリーランスでした。ハードウェアの設計や制作の仕事をしたり、東京造形大学などで非常勤もしたりしていました。
赤羽:その後ドイツへ?
菅野:文化庁の「新進芸術家海外研修制度」に選ばれて、ドイツに1年間いくことになりました。
赤羽:受け入れ先はどこですか?
菅野:ベルリン芸術大学(UdK)のユッシ?アンジェスレヴァのクラスに席を置いていました。
赤羽:文化庁の海外派遣で1年いて、そのまま残ったと。
菅野:そうです。ベルリン以外のところも少し見てみたくて、ロンドンにも一年くらい滞在したのですが、ベルリンの雰囲気の方が合っているなと思って。もう少しベルリンに住もうかなと。
赤羽:ビザはどうしているの?
菅野:大変でしたが、なんとかアーティストフリーランスビザを取ることができました。
赤羽:菅野のように、自分の作品を作ることだけで生活していくのは結構大変だと思うんですけど、どうやって続けてきたのですか。
菅野:それは勘違い力じゃないですかね。「なんとかなるでしょ」みたいな(笑)。
赤羽:いやいや。普通はお金が回らないと思うのだけど。いつからお金の心配をせずに生活できるようになったのですか?
菅野:僕もよく分からないです。吉野石膏とPOLAのグラントをもらってからですかね。日本よりも生活にかかるコストが安いという部分はあるかもしれません。
赤羽:ギャラリーに所属しているの?それとも直接依頼されるのですか?
菅野:サイトに直接連絡がきたり、例えば去年のフランスで参加した展覧会はやんツーから紹介されて。展覧会のディレクターが知り合いだったので、直接交渉して勝ち取りました。

赤羽:ということは、最初は文化庁からお金をもらいながら活動をして、そこから上手く軌道に乗せていこう、展覧会などをしながら、ここまで来たという感じなんですね。
ヨーロッパにはグラント(補助金)だけ狙っていく人もいるけど、あまり大成はしていない印象がある。だからある程度育ててもらったら、飛び立たなきゃいけないと思うのだけど、今そういう時期に来ていると思いますか。
菅野:東浩紀さんが『クォンタム?ファミリーズ』という本の中で「35歳問題」ということを書いていて。それは、35歳という年齢が今までやってきたこととこれからできることの分水嶺というような話なのですが、28歳くらいの時にそれを読んで興味深いなと思って、35歳以上の先輩たちにどうなんだろうと聞いて回っていたんです。その時にクワクボ(リョウタ)さんが、「35歳までに自分という名前のロケットが衛星軌道に乗るか乗らないかで、その後の展開が決まってくる」みたいなことを話していて。あれから7年経って、今僕34歳なんですよ。まだ軌道にいってない気がして、ちょっと怖いなとは思っています。
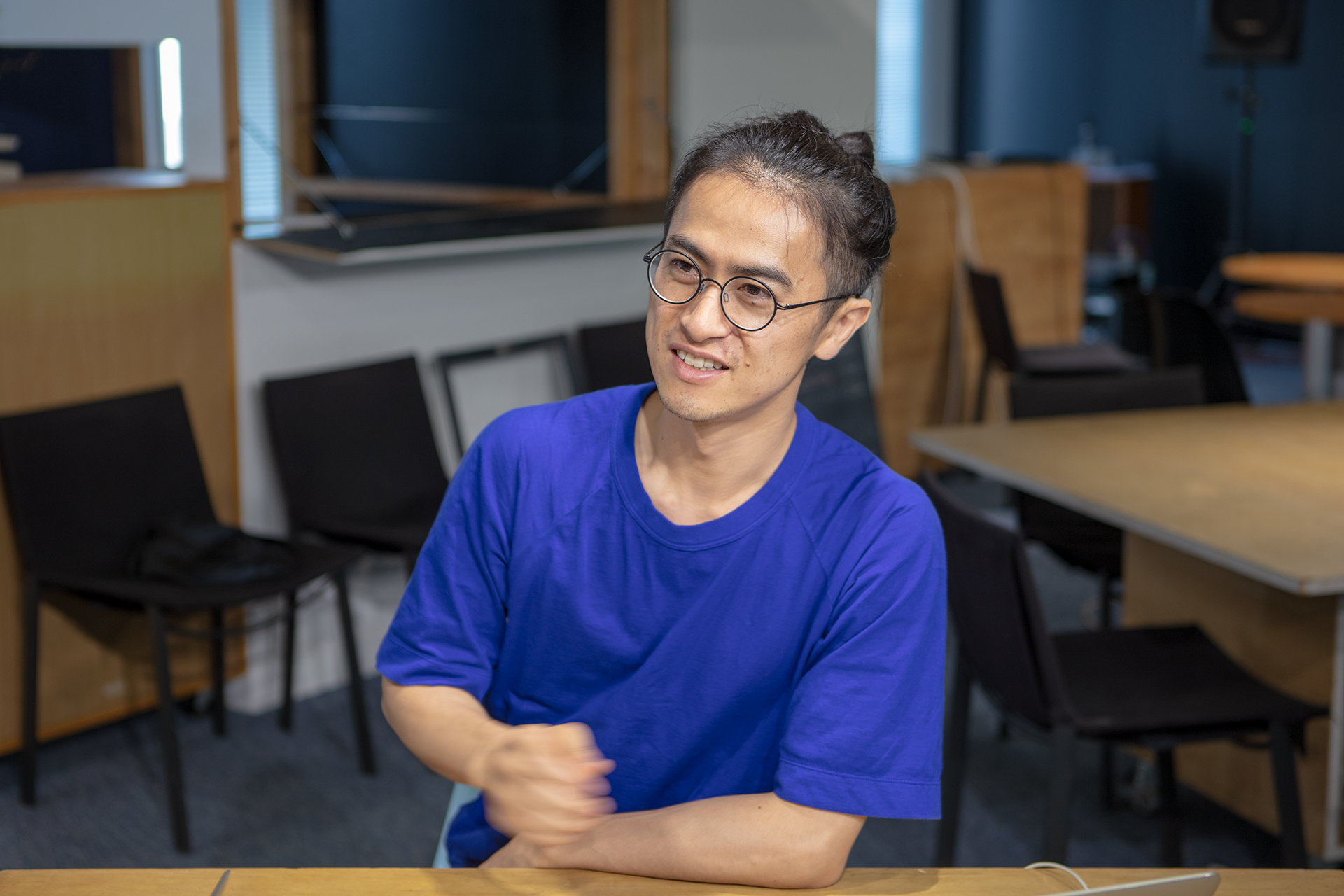
赤羽:乗れてるか乗れていないか、微妙なところなんだね。思うのは、菅野は普通の現代美術の枠組みで発表している訳ではないし、日本を売りにしている訳でもない。メディアアートの本流とも少し違うと思う。どこから見ても、他者みたいな位置にいるんだろうなと感じています。
現代美術やメディアアートの枠組みの中でどう勝負するかというよりは、全然違うところに立って、そういう既存分野に問いかけるみたいな立ち位置みたいなのかなと。
菅野:そっちの方が興味ありますね。
赤羽:ただそうなると、ここからは積み上げが難しい。だから逆にいろんなことに手を出して、どんどん違うところにいく方がいいんじゃないかなと思います。
菅野:僕もそうしようと考えています。
赤羽:今までの作品の中で、異色だったのはファッション(『Computed Copy』)とジャスティンビーバーの作品(『Captured Desire』)。これらは一般の人と直接仕事ができそうな話ですよね。さっき話したように、オーセンティックなアートじゃないところに手を出していくのが目指すべきところだとしたら、こういうところをもう少し深堀していってもいいかなと感じたんだよね。

『Computed Copy』ヌケメ+菅野創+やんツー
菅野:なるほど、確かにそうですね。
赤羽:率直に、将来的にはどうしたいと考えているのですか。
菅野:正直あまり考えていないですね。最近冗談で、「ロボットのお医者さんになる」と言うことはありますが…。
赤羽:ロボットのお医者さんとは?
菅野:これからロボットがたくさんできるようになって、愛着を思って触れられうる機械が増えてきた時に、メーカーだけでは対応できなくなる。ロボットを直したいというニーズが増えるだろうし、そういう人たちの話を聞くのもおもしろそうなので、あと10年くらいしたら、趣味でドクターをやろうかなと。
赤羽:なるほど。でもそれは創作意欲に繋がるというか、「人が機械をどう学べるか」というやりたい部分に触れているんじゃないかな。
菅野:そうですね。それで起業しようとかはあまり考えてないですね。35歳まであと1年で、ある程度仕事の話も来るようになったし、今回賞もいただいたんですけど、それが軌道からどれくらいなのかは正直分からない。だから今はクワクボさんに会って話がしたいです(笑)。
